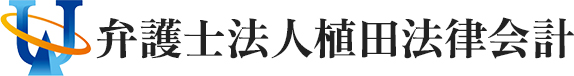コラム
~弁護士が解説する!絶対に抑えておくべき離婚のキホン(その2の1)~
2025年7月10日
~弁護士が解説する!絶対に抑えておくべき離婚のキホン(その2の1)~
さて、前回の第1回目のコラムから約2年半そのままとなっておりました、離婚のキ・ホ・ンのその2について、弁護士植田が解説していきたいと思います。
この知識は、離婚調停をする上で前提として、是非とも知っておいてもらいたいものになります。
前回の「離婚のキホンその1」では、①協議離婚についてお話させていただきました(~弁護士が解説する!絶対に抑えておくべき離婚のキホン(その1)~ – 弁護士法人植田法律会計)。
今回は、②調停離婚について、お話します。
文章量が多いため、2分割でお送りします。
(1)調停離婚
家庭裁判所のHPをみてみると、調停離婚の概要について、「離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,離婚そのものだけでなく,離婚後の子どもの親権者を誰にするか,親権者とならない親と子との面会交流をどうするか,養育費,離婚に際しての財産分与や年金分割の割合,慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。」と解説されています。
前回の①協議離婚がまとまらない場合には、次のステップとして、家庭裁判所が関与する離婚調停を行うことになります。正式には「夫婦関係調整調停(離婚)」となります。なお、「夫婦関係調整調停(円満)」という調停もあり、これは円満調停と呼ばれ、行き違いになった夫婦の関係修復に裁判所が関与する手続きもあります。
離婚する夫婦全体の約9%がこの離婚調停により離婚しております。年間の離婚件数が約19.3万組(令和2年度)なので、約1.7万組が調停離婚となっていることになります。
(2)離婚調停の流れ
ア 離婚調停では以下の流れで進みます。
①家庭裁判所へ離婚調停の申立
②調停期日の調整・通知
③第1回調停期日
④第2回調停期日
⑤調停期日を繰り返す
⑥調停成立or不成立or成さず
イ それぞれの解説(※弊所は大阪家裁の利用が多いため、他の裁判所では取扱が異なることがございます。)
①家庭裁判所へ離婚調停の申立てを行います。離婚調停の申立書は家庭裁判所のHPにありますのでご参照ください(弊所では当該雛形ではなく弁護士が別途申立書を作成します。)。印紙、郵券、添付書類(戸籍謄本)等とともに家庭裁判所の事件受付係に提出します(郵送可)。
離婚調停と同時に婚姻費用分担請求調停も申し立てることが多く、同時申立の場合には、戸籍は1通で良いというルールがあります。
どの家庭裁判所に提出するかに関しては、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります(例えば、夫=申立人・東京在住、妻=相手方・大阪在住の場合、大阪家庭裁判所が管轄裁判所となります。)。
②離婚調停の受付けがなされると、各家事の係に申立書が回され、書記官のチェックの後、調停期日の調整を申立人と行います(電話)。そのため、第1回調停期日は申立人と裁判所の都合により決定されます。
調停の申立てから第1回期日を迎えるまでは1~2ヶ月程度はかかります(各家庭裁判所や時期による。)。
第1回目の調停期日までに、子に関するビデオを視聴したり、現在の生活状況に関しての回答書を作成して提出することがよくあります(形式などは裁判所による。)。
③第1回目の調停期日では、調停委員の自己紹介、出頭者の身分確認が行われます。そこから、申立書に沿った事情の聞き取りが行われます(離婚原因、別居の経緯、子供のこと、その他心配事など)。
調停委員と話をする調停室へは、当事者本人(+弁護士)しか入ることができません(家族、その他付添人は別の待合室で待機することになります。)。
調停期日では、申立人と相手方は時間をずらして集合時間が指定されており、待合室も別となりますので、お互いに顔を合わせることはありません(早めに裁判所に来ていたり、裁判所の構造上会うことになる場合があるかもしれません。)。
第1回目の調停期日では、上記話の聞きとりがメインで、大きく話が進むことはほぼありません。また、調停1回分は2~3時間程度であり、調停室へは1回30分を2~3回、相手方と入れ替わる程度で終わります。
第1回目の調停の終盤では、それぞれに宿題が与えられ、第2回目の調停期日の調整がなされます。
④第2回目の調停期日では、前回期日での宿題を前提に、争点となっている点を整理していくことになります(協議離婚で決着が付かなかった夫婦のため、何かしらの争点があるはずです。)。そして、争点について、裁判所の立場から双方の話を聞いていきます。
⑤その後は、第2回目の調停と同様に調停期日を繰り返していきます。調停期日の間隔としては1ヶ月~2ヶ月に1回のペースで行われます。ある程度議論が煮詰まってくると、調停委員会(調停委員+裁判官)の意見として提案してくることがあります。
⑥最後申立人・相手方間で合意に至れば、調停成立となります。調停が成立すると、裁判所の書式で話合いの内容をまとめ、その結果を裁判官が読み上げて間違いないかを確認してくれます。
調停が終盤になると、双方の気持ちが変わらないようにと、最後にバタバタと調停の合意を取り決めることが多いのですが、難しい法律用語で早口に調停の内容がまとめられるので、しっかりと読み上げられた内容を確認することが大切です(後からひっくり返すことは極めて困難です。)。他方、これ以上調停を続けても成立の余地がないと調停委員会で判断した場合には、調停は不成立との判断がなされます(この場合、次のステップである離婚訴訟に進むことになります。)。その他、あまりありませんが「成さず」との判断となることもあります。
(3)離婚調停で決めること、(4)離婚調停の効力、(5)弁護士に依頼するべきか
に関しては~弁護士が解説する!絶対に抑えておくべき離婚のキホン(その2の2)~において、お話したいと思います。
弁護士 植 田 諭