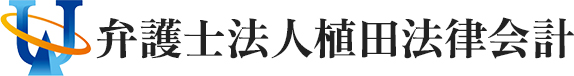コラム
~弁護士が解説する!絶対に抑えておくべき離婚のキホン(その2の2)~
2025年7月20日
~弁護士が解説する!絶対に抑えておくべき離婚のキホン(その2の2)~
さっそく、前回の続き(前回の投稿はこちら)からお話していきます。
(1)調停離婚 前回投稿を参照
(2)離婚調停の流れ 前回投稿を参照
(3)離婚調停で決めること
メインとして離婚と親権を決めることになります。
それに付随して、慰謝料、養育費、面会交流、財産分与、年金分割等を決めることができます。
調停は話合いの場なので、その他のこと(健康保険証を返して欲しい、物を返して欲しい等)も柔軟に話合うことができます(ただし、話のメインにはなりません。)。
(4)調停調書の効力
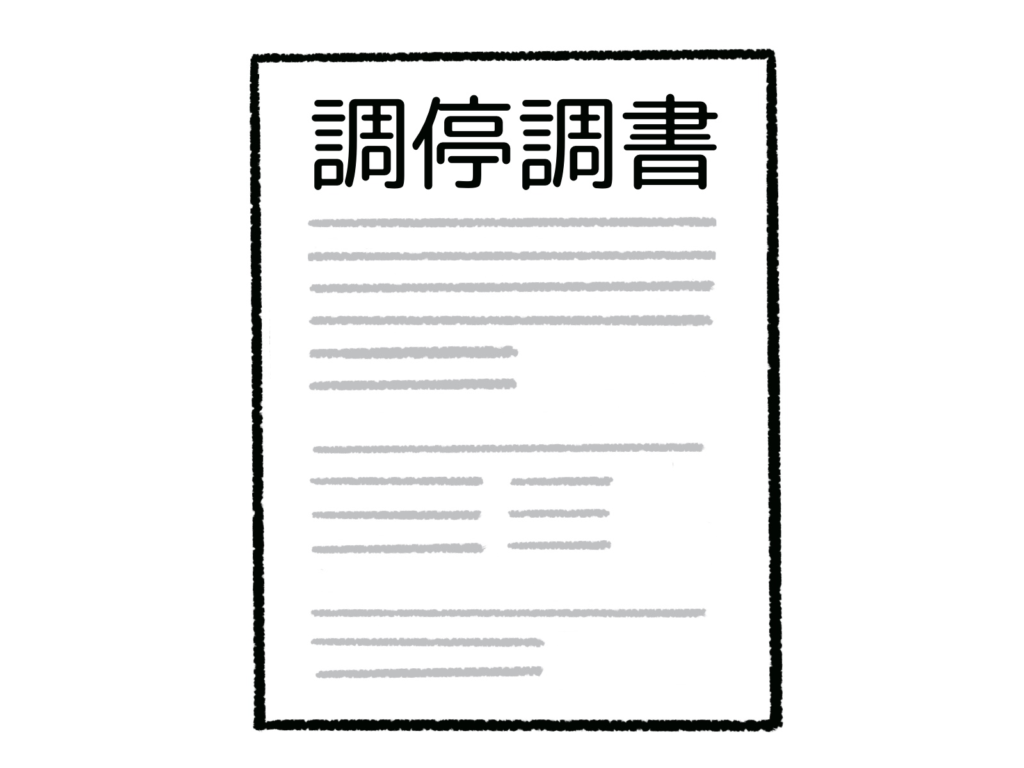
離婚調停が成立すると、調停調書が作成され、これは裁判所が作成したものである以上、とても強い効力を有しています。
離婚はどちらか一方が相手方のサインなくして離婚届けを役所に提出することができます。
また、慰謝料、養育費などに関しても、不払いがあれば、すぐに強制執行(給与の差押え等)をすることができるようになります。
(5)弁護士に依頼するべきか

「離婚調停となったら弁護士をつけなくては!」と思いの方はそれなりにいるようです。私としても離婚調停から、是非とも弁護士に依頼することをご検討いただきたいと考えています。
なお、離婚調停において弁護士をつける割合としては50%以上となっており、年々増加する傾向にあり、多くの方が弁護士の依頼を検討されています。
弁護士にいただく場合のメリット
①離婚の最適解を得ることができます。
→調停委員はあくまで中立的な立場にしかなく、貴方に適切なアドバイスをくれません。法律上は明らかに貴方にとって有利な事情でも相手方がごねることで貴方にとって不利な提案をすることもあります(調停委員は調停を成立させることが目的です。)。弁護士は、離婚における相場観や落としどころをある程度予測しながら、弁護活動を行います。そのため、貴方にとっての最適解により近づくことができます。
②離婚手続きの煩雑さの解消
→弁護士は上記で説明した離婚の手続きに精通しておりますので、各種手続きにおける手間・時間を最小限で進めることができます。また、貴方が裁判所に出頭できない場合には、弁護士のみで代わりに調停期日に参加することができます。調停期日は平日の昼間に行われますので、毎度有給をとらなくてもよいということにもなります。その他、離婚成立までの各種手続きも代行してくれます。
③良き相談相手
→離婚問題は、年収、仕事、子供のこと、不倫、暴力、親族関係、その他家庭の事情が絡む内容となっていることが多く、なかなか周りには相談できない内容かと思います。弁護士は守秘義務を負っていますので他言は致しませんし、仕事として向き合っているので安心して、色々なことを相談することができます。また、調停室にも同行できますので、実際の調停委員とのやりとりや相手方の主張に対する反論や考え方等の助言を受けることができます。その意味で、弁護士は非常に心強い存在になります。
④調停期日間のやりとり
→離婚問題は、単に、離婚のことだけでなく、夫婦関係を清算していく手続きも随時していく必要があります(健康保険の切り替え、口座振替の変更、保険の変更、子ども手当の変更等)。それら調停では処理しきれない問題も弁護士が調整してくれます。また、調停は上記のとおり長期になってきますので、任意の面会交流、婚姻費用の支払い等でも関与してくれます。
弁護士に依頼いただく場合のデメリット
①費用がかかる
→弁護士を雇う以上、弁護士費用がかかってきます。弁護士を雇う場合、着手金、報酬金、実費、日当が発生します。また、法律事務所ごとで費用が異なるため注意が必要です(報酬金を「協議する」とだけ記載し、費用が不透明な事務所もあるようです。)。
なお、弊所では、弁護士費用を抑えるためにサポートプラン(サポートプランは、離婚調停での対応等を依頼者様自身でしていただくプランです。ライトプラン:5.5万円(税込)、通常プラン:22万円(税込))も実施しておりますので、是非ご活用ください。
いかがでしたでしょうか。離婚調停では、まだまだ説明しきれないところがありますし、貴方がご自身で手続きされる際にも、ぶつかる問題は多々あるように思います。そんなときは、是非弊所へご相談下さい。
初回30分無料にて相談も承っております。
離婚調停の代理の依頼だけでなく、サポートプランも完備しております。
法律問題、手続きの面で分からないことがあれば、わかりやすくアドバイスをしています。是非ご相談ください。
次回コラム「~弁護士が解説する!絶対に抑えておくべき離婚のキホン(その3)~」は、8月中に書くようにいたします。
弁護士 植 田 諭